外国籍の園児、保護者対応はどうすればよい?
- 保育士お役立ち情報
- 2021/02/17
外国人の増加に伴い、保育園で外国籍の園児の受け入れが増えています。それに伴い、保育士にも特別な対応が必要になってきています。外国籍の園児・保護者の対応について、注意点や心構えなどを紹介します。

外国籍の園児は増えている!?
日本で働く外国人が増加傾向。伴い外国籍園児も増加!
厚生労働省の調査によると、日本で働く外国人は約166万人と過去最高になっています(2019年10月末時点)。ちなみに国籍では、中国が最も多く、次いでベトナム、フィリピンの順になっています。
日本で働く外国人の増加に伴って、保育園に通う年齢(0〜6歳)の子どもも増えています。その数は2012年から19年の7年間で約1.4倍に増加しています。
ある調査では、外国籍の保護者のほとんどが子どもを保育園に預けていることがわかっています。そうした数字からも、保育士にとって、外国籍の子どもが身近な存在になってきているのがわかりますね。
さらに、外国籍の子どもの家庭の半数は、日本語以外の言葉を家庭で使用しているそうです。そのため、日本語に慣れるまで時間がかかり、受け入れ先の保育園では、園児・保護者双方のコミュニケーションで課題を抱えることになっているのです。
しかしながら、そうした事態に対する国としての対応やガイドラインは存在していません。各保育園の対応に任せられているのが現状です。
外国籍の園児に対する困りごととは?
コミュニケーションにおける困りごとが多い!
外国籍の子どもの保育では、主にコミュニケーションにおいて様々な困りごとが発生しています。その代表例は以下となっています。
外国籍の子どもに感じている困りごと例
・日本語がわからないので、意思疎通が難しい。
・指示しても理解してもらえない。
・まったく話をしようとしない。
・絵本を読んでも内容が伝わりにくく、集中できない。
・言葉に関する発達の程度がわかりにくい。
そんな困りごとについての対応策も紹介します。
外国籍の子どもへの対応例
・日本語をゆっくり、はっきり話す。
・母国の生活に関する遊び、教材を保育に取り入れる。
・近くに座る、手をつなぐなどの個別の働きかけを行う。
・わかりやすくイラストなどで見せる。
・「おはよう」などのあいさつは母語で行う。
外国籍の子ども対応は時間とともに解消する!?
日本語の理解が飛躍的に向上するため解消される!
現場の保育士であれば実感していることですが、当初苦労していた外国籍の子どもの対応も、時間がたつとだいぶ楽になっていきます。 文部科学省の統計でも、約半数が入園から半年程度で、当初気になった姿が見られなくなるとされています。
その理由としては、時間とともに日本語の理解が飛躍的に進むことにあります。この年齢の子どもは言語習得能力が高いため、自然と言葉を覚えていきます。入園から半年もすると、格段に意思の疎通がしやすくなるのです。
よって、外国籍の子どもについては、あせらず無理をせず徐々に日本の生活に慣れていけるよう保育士がサポートしてあげることが必要です。そうすることで、問題なくなじんでいくことがほとんどです。
ほかに保育園側が配慮すべきことは?
宗教・文化・習慣の理解!
他に保育園側が配慮すべきこととして、宗教・文化・習慣の理解などが挙げられます。これは園全体での配慮が必要になります。
例えば、宗教上の理由でイスラム教徒は豚肉を食べることが禁じられています。そのため、イスラム教徒の園児には給食の食材を別の物に代えて提供している園もあるようです。
外国籍の保護者対応で困ることは?
「伝えたいことをうまく伝えられない」ことが多い!
外国籍の保護者に保育士が感じている困りごととして「伝えたいことをうまく伝えられないこと」の割合が最も高いようです。
以下で、困りごとの例を紹介します。
外国籍の保護者に感じている困りごと例
・園だより等の印刷物の内容が伝わらない。
・園の決まり、重要な連絡事項を理解してもらえない。
・子どもの様子(友人関係、体調など)を伝えられない。
・外国籍の保護者が他の保護者と意思疎通できずに孤立している。
・子どもの体調について「大丈夫」の感覚が日本人と異なっている。
子どもの場合とは異なり、保護者に関する困りごとの解決は難しい傾向があります。それは、日本語の習得が難しい年齢であることも大きな要因です。時間とともに意思の疎通ができるようになっていきますが、そのスピードはゆっくりの場合があります。
そのため、保育士側で工夫してコミュニケーションする必要が出てきます。
コミュニケーションの工夫例
・連絡帳、お便りの読んでほしい箇所に下線を引いたりするなど、わかりやすく工夫する。
・連絡帳、お便りは翻訳ツールなどで翻訳して用意する。
・子どもの持ち物は、現物を見せながら説明する。
・スマートフォンの翻訳ツールなどを使ってコミュニケーションを行う。
・両親どちらかが日本語ができる場合、そちらの保護者を主な窓口にする。
保育園の国際化に伴い、横浜市では外国人相談員の派遣を行っています。相談員は日本語がわからない保護者と保育園側の間の通訳、お便りなどの翻訳を行うほか、子どもと一緒に過ごすなど、橋渡し役を務めているそうです。
そうした仕組みがないか、管轄の自治体に問い合わせてみることもおすすめします。
まとめ
外国籍の子どもや保護者にとって、保育園は日本での生活の重要な窓口になります。特に子どもにとっては集団生活も初めてのことが多く、不安いっぱいの場合もあります。そのため、保育士は子どもの気持ちに寄り添って、根気よく働きかけをしていく必要があります。
保護者についてはコミュニケーションに工夫をしながら、異国での子育てをサポートしていきましょう。
ライタープロフィール
玉田 洋さん
保育園運営企業で、子育て雑誌編集長を経験し、その後、都内で保育士として勤務する。現在は「森の保育園」を計画中。

保育士.net LINEでは、保育士新着求人や保育の関連記事も配信♪
保育士.net LINEは『こちら』
\このページをシェアする/
 年上の後輩保育士との接し方に悩んだら?
年上の後輩保育士との接し方に悩んだら?
 保育士のお休みって実際どうなの?制度などもあわせて解説!
保育士のお休みって実際どうなの?制度などもあわせて解説!
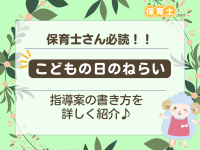 保育園での「こどもの日」のねらい、指導案の書き方を紹介!
保育園での「こどもの日」のねらい、指導案の書き方を紹介!
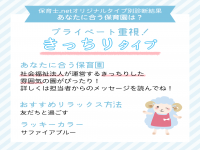 ★保育士netオリジナル★〜タイプ別診断【あなたに合う保育園は?】〜にご回答いただいた方へ
★保育士netオリジナル★〜タイプ別診断【あなたに合う保育園は?】〜にご回答いただいた方へ
 パワーハラスメントにならない指導の仕方3
パワーハラスメントにならない指導の仕方3
 意外と知らない!おなじみ「モンテッソーリ教育」ってどんなもの?
意外と知らない!おなじみ「モンテッソーリ教育」ってどんなもの?
 ピアノが弾けない!苦手な保育士必見のピアノ上達方法
ピアノが弾けない!苦手な保育士必見のピアノ上達方法
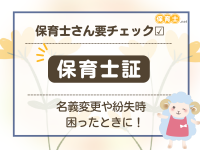 【保育士証】名義の変更や紛失などの届け出はどうしたらよいの?
【保育士証】名義の変更や紛失などの届け出はどうしたらよいの?
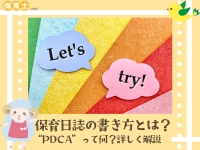 保育士の仕事【保育日誌の書き方】
保育士の仕事【保育日誌の書き方】
 保育園での熱中症対策で気をつけることは?症状・対処方法を解説。
保育園での熱中症対策で気をつけることは?症状・対処方法を解説。
 挑戦編
挑戦編
 復帰編
復帰編
 転職編
転職編
 新卒編
新卒編