乳幼児の噛みつき対処法は?ポイントは心のケア!
- 保育士お役立ち情報
- 2021/09/08
保育園の乳児クラスで起こるトラブルに「噛みつき」があります。昔から現場の悩みだった噛みつきですが、実は子どもの発達に深く関わっています。保育士なら知っておきたい、噛みつきについての知識、対処法について紹介します。

噛みつきはなぜ起こる?
一般的に「自分の気持ちを表現する一つの方法」と言われている!
ある研究によると、噛みつき発生のピークは18ヶ月~ 28ヶ月頃(1、2歳児)に集中して発生します。なぜその年代の子たちは、噛みつきをするのでしょうか。
その原因については保育現場でもさまざま言われていますが、時に「親の愛情が不足しているから」と語られることがあります。しかし、これは医学的な見地からは全く根拠のない話だそうです。今でもそのように語る保育士がいますが、安易に保護者に責任を転嫁することになり、注意が必要です。
一般に噛みつきの起こる要因については、自我が芽生えはじめた乳幼児が自分の伝えたいことをうまく表現できず、自分の気持ちを表現する一つの方法として衝動的に噛みついていると考えられています。ただし、詳しい原因について医学的な見地からははっきりとは分かっていません。
一つの原因ではなく、条件が重なり合って発生するものと考えたほうがいいようです。
おもな噛みつきを起こす3つ原因とは?
①自己表現の手段
乳幼児は言葉が発達途中なので、自分の気持ちを言葉で表現することが不十分です。そのため、噛みつきは自己防衛の一つとして発生します。
例えば、自分が使っていたおもちゃをお友達に取られた時も「やめて!」とは言えずに、とっさに噛みつきが出てしまいます。3歳前後で噛みつきが消失するのは、言葉が話せるようになり自分の思いを語れるようになるためです。
②友達関係の始まり
乳幼児の「一緒に遊びたい」「相手をして」「ぼくにも貸して」という関わりたい思いから、噛みつきがはじまっているとも考えられています。この年齢の子たちは、友達に関心を向けることはできてもどうすれば相手が喜んでくれるか十分にはわかりません。それが攻撃行動に見えることがあるのです。
③保育園という環境の問題
噛みつきは保育園特有の悩みです。保育園で噛みつきが頻発するのは、その環境にも理由があるようです。ある研究者は、保育園は一律のプログラムのもとで過密な環境の中で子どもを保育しようとしているため噛みつきが発生しやすいという見解を述べています。
例えば、昼食前後に噛みつきが増加することがわかっていますが、その時間は保育士の目が行き届きません。さらに、子どもも一ヶ所に集められて緊張感が高まっているので、噛みつきが発生しやすくなっています。これは保育園ならではの環境といえます。
実際に噛みつきがあった際の対処方法は?
子どもへの対処方法を紹介!
噛みつきが発生してしまった場合、どのように対処・予防していったらいいのでしょうか。いくつかの例で紹介します。
噛んだ子への注意の仕方について
噛んだ子に対しては「噛みつきは良くないことだよ」と、しっかり丁寧に伝えることが大切です。また噛まれた子が痛い思いをしていることも伝えましょう。また「次は噛まずに、ちゃんと貸してって言おうね」など、その場で教えてあげることも大切なポイントです。これは根気よく続けていく必要があります。
逆に、保育士は噛んだ子に対して「この子は噛む子」と常に緊張感を持って接するのはNGです。それが精神的に追い詰めることになり、余計に噛むなどの悪循環になる可能性もあります。
噛まれた子への声がけについて
噛まれた子に対しては、噛まれた跡が残らないように流水で冷やしてあげましょう。そして「噛まれて痛かったよね。〇〇くん、××ちゃんに貸してって上手に言えなかったんだね」など、噛まれてしまった子に対してその気持ちに寄り添って言葉をかけてあげましょう。
噛んだ子を責めるのでなく、その気持ちを代弁してあげることも大切です。
保育士は、噛んだ子、噛まれた子双方の気持ちを汲み取り、代弁していくことが、心のケアになり再発の予防にもつながります。
保護者への対処方法も紹介!
保護者への働きかけは、各園の方針によって対応が異なってきます。以下を参考に、園長や主任と相談しながら進めましょう。
噛んだ子の保護者への伝え方について
噛んだ事実だけを保護者に伝えると、保護者は自分の愛情が足りないからではないかなどで自分を責める傾向があります。できるだけ丁寧に噛みつきが起きた経緯を伝え、その子に対して保育士が行ったケアや言葉がけも伝えて安心してもらいましょう。
また、噛まれた子の名前を教えて欲しいと言われることもあります。一般的には個人名を伝えることはありませんが、最近は親同士の関係も考慮して伝える園も増えているようです。
噛まれた子の保護者への伝え方について
傷の有無に関わらず、噛みつきが防げなかったことを謝罪しましょう。噛まれた時の状況を詳細に説明し、応急処置などの対応についてもしっかり伝えることが不信感を残さないために大切です。
保育現場で噛みつきが発生した場合、それがきっかけで保護者に不信感を抱かせることがあります。それが悪化すると、噛みつきが原因で保育園を退園する保護者もいるようです。
保護者の心のケアも保育士の重要な仕事だと考えて接してください。
まとめ
噛みつき自体は、子どもの発達の中で発生するごく当たり前の現象です。よって、その子の心の発達とともに必ず沈静化していきます。
ただし、保護者にはそうした知識がなかったり、過剰に反応することもあります。
また、それが子ども同士の関係に反映するなど、噛みつきを巡っては保育環境に良くない影響が出る場合があります。保育士は噛みつきについてきちんとした知識と見解を持って、子どもと保護者の心のケアをしていくことが必要です。
ライタープロフィール
玉田 洋さん
保育園運営企業で、子育て雑誌編集長を経験し、その後、都内で保育士として勤務する。現在は「森の保育園」を計画中。
保育士として就転職をお考えの方へ
【保育士.net】コーディネーターへお気軽にご相談を
保育士として就転職を始めようと思っても、自分の希望に合った保育園を探すのはなかなか大変と感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
【保育士.net】では、保育士現場にも詳しいコーディネーターが希望に合った保育園の求人情報を紹介。お気軽にご相談ください。
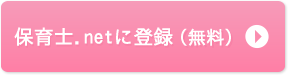
『保育士.net』お役立ち情報
『保育士net』では、LINEやyoutubeなどSNSにて保育関連情報を配信しています。ご興味ある方は、ぜひこちらもご覧ください。
保育士.net LINE
保育士.net LINEでは、保育士新着求人や保育の関連記事も配信♪
保育士.net LINEは『こちら』
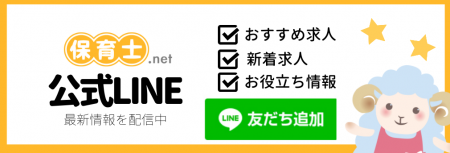
保育士net YOUTUBE
保育士netでは「ほいくるんTV」を配信中♪
ほいくるんTVは『こちら』
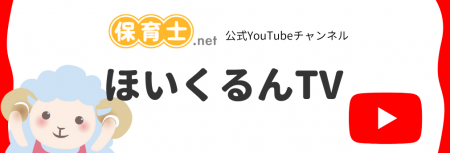
\このページをシェアする/
 【保育園での節分】おすすめの製作物・あそびは?
【保育園での節分】おすすめの製作物・あそびは?
 保育士の待遇は年々改善されている!?保育士の「処遇改善加算」とは?
保育士の待遇は年々改善されている!?保育士の「処遇改善加算」とは?
 同僚は発達障害かも?と思ったら3~理解と連携のコツ(ASD編)~
同僚は発達障害かも?と思ったら3~理解と連携のコツ(ASD編)~
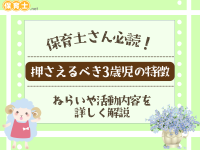 【3歳児の保育】ねらいや活動内容など、保育士が押さえるべき3歳児の特徴
【3歳児の保育】ねらいや活動内容など、保育士が押さえるべき3歳児の特徴
 保育士にとっての働き方改革って?
保育士にとっての働き方改革って?
 保育士さん必見!子どもと一緒に楽しめる♪パネルシアターをはじめよう!
保育士さん必見!子どもと一緒に楽しめる♪パネルシアターをはじめよう!
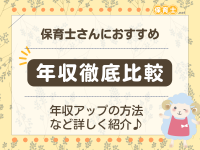 【保育士の年収】年齢、勤務年数、公立/私立、幼稚園教諭比較など徹底紹介!
【保育士の年収】年齢、勤務年数、公立/私立、幼稚園教諭比較など徹底紹介!
 保育園栽培に最適!美味しくて簡単なベリーを育ててみよう
保育園栽培に最適!美味しくて簡単なベリーを育ててみよう
 年齢別の絵本の選び方【0歳児~2歳児編】
年齢別の絵本の選び方【0歳児~2歳児編】
 今年こそ目標を達成してみませんか?
今年こそ目標を達成してみませんか?
 挑戦編
挑戦編
 復帰編
復帰編
 転職編
転職編
 新卒編
新卒編