保育士の住宅支援制度早わかり&自治体ごとの実施状況[最新版]
- 保育士お役立ち情報
- 2022/12/21
保育士の待遇改善策として、積極導入されるようになった住宅支援制度。一人暮らしで保育士の仕事をしたいという方の強い味方となっています。
一口に住宅支援制度といっても、大きく分けて3つのパターンがあります。それぞれのメリットと注意点、自治体が実施する保育士住宅支援の最新情報をお届けします。
(最終更新:2022年12月21日)
≪保育士.netでは、首都圏で就業をお考えの保育士の皆さまの力になれるよう、面接にかかった交通費をキャッシュバックを実施しています。
→最大3万円の交通費が受け取れる制度をみる≫

パターン1:借上げ社宅制度(会社が社宅を用意)
勤務先の会社が契約している物件(アパート・マンション)に居住し、家賃の一部が自己負担分として毎月の給与から天引きされる、会社独自の福利厚生制度です。住居は配属園の近隣で用意してもらいます。
※本人負担額は法人によって異なりますが、月額1〜3万円、あるいは家賃の6〜8割といったものが増えています。
メリット
・会社が契約するので初期費用&更新料ゼロ。
・自分で借りる(住宅手当)より、毎月の家賃負担額が更に安い。
注意点
・就業前の現住所によって利用できない場合アリ。(対象者が首都圏以外の地方在住者であったり、現住所からの距離の条件が厳密に規定されるため)
・物件の選択肢が限られている。
・入居可能年数の規定がある。
パターン2:住宅手当(毎月手当として支給される)
毎月の給与に、手当として支給されます。借り上げ社宅と同様に会社独自の制度であるため、会社によって金額や規定は大きく異なります。
※手当の金額は法人によって異なりますが、月額手当1〜2万円(就業前の居住地域によって変動)が主流です。
メリット
・物件、場所は自分で自由に決められる
注意点
・賃貸の世帯主(契約者本人)であること、単身者といった規定が多い。
パターン3:行政の住宅支援制度(保育従事職員宿舎借り上げ支援事業)
保育士確保を目的に、自治体が保育運営事業者に対して住宅支援金を補助する制度です。会社の借り上げ社宅の居住が条件にになっています。待機児童問題の深刻度が高い首都圏を中心に各自治体で実施されています。
メリット
・家賃のほとんどを補助でまかなうことができる。
たとえば、千代田区は上限130,000円(千代田区内に住んだ場合)まで補助されるなど、負担を感じずに入居することができます。
注意点
・居住が就業園と同区内かどうか、実務経験5年以下であることなど、自治体ごとに細かな規定が異なります。
各都道府県の家賃補助の詳細と注意点は下記からご確認ください。
\このページをシェアする/
 保育士の労働時間・勤務制度って一体どんなものがあるの?
保育士の労働時間・勤務制度って一体どんなものがあるの?
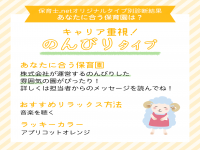 ★保育士netオリジナル★〜タイプ別診断【あなたに合う保育園は?】〜にご回答いただいた方へ
★保育士netオリジナル★〜タイプ別診断【あなたに合う保育園は?】〜にご回答いただいた方へ
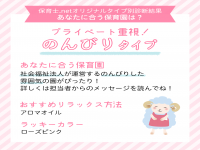 ★保育士netオリジナル★〜タイプ別診断【あなたに合う保育園は?】〜にご回答いただいた方へ
★保育士netオリジナル★〜タイプ別診断【あなたに合う保育園は?】〜にご回答いただいた方へ
 ≪現役保育士さん必見≫保育士向け制度まとめ〜千代田区編〜
≪現役保育士さん必見≫保育士向け制度まとめ〜千代田区編〜
 保育士さん向け【令和4年度版】東京23区自治体別・補助制度のご紹介
保育士さん向け【令和4年度版】東京23区自治体別・補助制度のご紹介
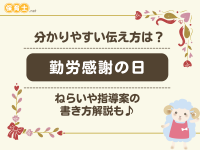 勤労感謝の日のねらい、指導案の書き方を紹介!
勤労感謝の日のねらい、指導案の書き方を紹介!
 保育士が気になる「退職金制度」私立保育園の最新事情は?
保育士が気になる「退職金制度」私立保育園の最新事情は?
 1年目の保育士が辞めたい6つの理由!対処法も解説
1年目の保育士が辞めたい6つの理由!対処法も解説
 「手遊び歌」の効果を最大限引き出す!ねらいと実施時のコツを紹介します
「手遊び歌」の効果を最大限引き出す!ねらいと実施時のコツを紹介します
 【年齢別】効果的な子どもの叱り方とは?
【年齢別】効果的な子どもの叱り方とは?
 挑戦編
挑戦編
 復帰編
復帰編
 転職編
転職編
 新卒編
新卒編